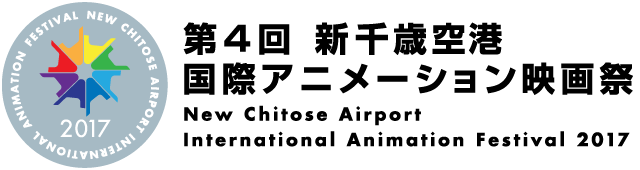映画祭レポート②/リュウ・ジアン特集『HAVE A NICE DAY』

リュウ・ジアン氏
映画祭2日目の最終プログラムを飾ったのは「リュウ・ジアン特集『HAVE A NICE DAY』」。本映画祭の短編アニメーション・コンペティション国際審査員を務める映画監督のリュウ・ジアン監督をお招きし、中国の長編アニメーションとして初めてベルリン映画祭にノミネートされた作品『HAVE A NICE DAY』の上映と、メイキング・トークが行われた。
中国南部の小さな町、美容整形手術に失敗した婚約者を救うための資金を必死に獲得しようとするシャオ・チャンは、百万元が入ったカバンを上司から奪う。この強盗事件からシャオ・チャンと金をめぐり人々の欲望が絡み合う一日が幕を開ける。
『HAVE A NICE DAY』というタイトルとは裏腹に、描かれる登場人物たちは、大金に目がくらみ犯罪や暴力によってその金を奪い合う。序盤だけ見ればハードな作品なのかと思わされる。さらに最初に金を奪ったシャオ・チャンと、彼と関わりのある人間、さらには全く関わりのなかった人間と、様々な人間が強奪戦に参加し、金を奪い合うことで、彼らの運命が複雑怪奇に絡みあう。しかし、犯罪と暴力による負の連鎖が、終盤へ向かうにつれ笑いを生む仕掛けとして積み上げられたものであったと気づいた時には、リュウ監督が描く”ブラックユーモア”の虜になり、物語の終わりへと差し掛かる頃には会場からは思わず笑い声が出るようになっていた。

『HAVE A NICE DAY』
リュウ監督は「ユーモアの表現は映画にとって重要です」と言う。「犯罪や暴力的な要素を通して世の中の現実を表すと同時にブラックでハードな表現を入れることで、リアリティあるユーモアを描けるようになります。(中略)この映画の中で登場人物たちは金に目がくらみ、その欲望から犯罪や暴力を行います。それが超現実主義な環境を作り出すのです。金を手に入れたあとを想像して突然歌い出してしまうような陽気さや、次々に起こる負の連鎖がブラックユーモアとなることを通じて、語りたいことを表現しているのです」と語るのだ。
そしてリュウ監督は、自身がアニメーション監督になった経緯を語ってくれた。「十数年前に、それまでの自分の芸術のスタイル(絵画)では、表現したい世界や人そのものの理解と思考に間に合っていなかった。そんななか、もっと自分に合う芸術的な言語表現を探して出会ったのがアニメーションでした。(アニメーションという豊富な芸術スタイルは)、伝統的な技術や美学などの要素に限定しないでいれば、自由で多彩な物語の形式に挑戦できるような複雑性を持っているのです。」
クリエイターとして、アニメーションとの出会いは興奮を覚えさえするものだったらしい。自身の作品作りについては、「素朴でシンプルであることが私のアニメーション作りの特徴です。カメラを固定することで実現する簡単で冷静なカメラの言語を通して、私からのメッセージを込めています」と話す。
今作『HAVE A NICE DAY』を制作する際には、「人物の情緒は細かな動作の描写を通して表現しました。一方、背景は写実的な表現を取り入れました。実際に中国にある都市をモデルに詳細に描くことで、詩的かつロマン的に、そして哀愁も交えて、郊外の都市風景を浮き彫りにしています」と語った。また、作中で最終的に登場人物たちがどうなったのかを明示しない人物描写の演出をすることで、「余白を残した」とも話した。

左:フェスティバルディレクター土居伸彰、中央:リュウ・ジアン氏、右:通訳の朴氏
トークの最後には、客席からのQ&Aの時間が設けられた。「作中、第三章冒頭に挿入された、実写の川の表現の意図は?」という質問に対し、リュウ監督は「余白を残して観衆への想像力を設けるものであり、敢えて何か解釈をすることはしなかった」と答えた。“余白”を散りばめることで、観る者の想像力を引き出す表現を作り出し、観客へと作品を委ねているのだと感じさせる。(ただし、質問の回答直後には「あえて答えるなら、一つはシャオが生きているのかどうかについての暗示、二つ目に人間の運命自体を波のようなものとして表現したかったからだ」とリュウ監督なりの“余白”への解釈を話してくれた。)
監督としてのこだわり、本作の設定や演出について話してきたなかで、最後、今作を表すキーワードとして“運命”という言葉を挙げた。「(この映画には)主役はいない。お金自体が主役。お互いに関係の無い人たちがお金によって関係付けられる。そんなとき、運命は選択によって決められる。彼らは運命に直面するが、それは自分の運命を選択する機会を得ているということなのだ」と話し、リュウ監督は今作を通して「誰でもこのようなゲームに参加することができるということを強調して伝えたい」と力強く語った。

リュウ・ジアン氏
今作は大金をシャオ・チャンが強奪するところから始まるが、この事件が起こったのは田舎の小さな町である。大都会で繰り広げられる大規模な逃走劇でもなければ、全くもって知り合いではなかった者同士が実は一人二人の人間を介すことですぐつながりあうような小さなコミュニティの中で起こった出来事であったことから、この物語は観客である我々の身近にも存在しうる“運命”の一つなのかもしれないと考えさせられた。
トークの最後では、映画冒頭で引用されていたトルストイの『復活』について語られた。その引用は、作品のメッセージと重なるものである。「どんな場所においても、春は依然として春です。どのような生活を送り、そこで何が起こったとしても、そしていかに運命を選ぶとしても、春は依然としてやってくるのです」と、作品に込めたメッセージを観客に送った。(編集局ボランティア)